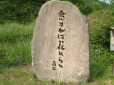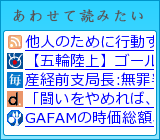右翼ではない。
山谷の件、たいそう反響があって嬉しい限りです。書くのに体力がいりますので、完結までもう少し待ってください。
#
今年大学に入った人はそろそろサークルが落ち着いたころでしょうか。
私のいた大学は多分日本でもサークルの活発さでは一二をを争うほどで、新入生の勧誘は、何百とあるサークルに加え、左翼団体の革マル派も加わり、それはもう大変な大騒ぎだった。
そうなると新入生歓迎の場所取りも必然的に熾烈な争いとなる。大学にきちんと場所を申請をしていても、その場所が勝手に取られたりするということも多い。
ある年、関口さんという人がその新勧の場所取りをまかされた。事前に大学に申請した場所にちゃんとガムテープ等で「サークルの場所はここですよ!」と印をつける役割だ。
関口さんは意気揚々と参加し、申請した場所を四角くガムテープで囲み、その中にガムテープでダイナミックに
「関口」
とそれはそれは大きな字を書いた。
翌日、サークル員が申請した場所に行くと大きな字で「関口」。みんな困惑するが、その中の一人が
「関口じゃあ、革マルに個人と思われてなめられます。」
と提案。ガムテープを取り出し、「関口」の上にビリビリとガムテープを貼っていく。そして、見る間に「関口」の字は
「関國共」
となった。意味はよく分からないが、とりあえず怖そうだ。これで今年の新勧は誰にも場所をよこどられることないだろう、とみんな胸をなでおろしていると、どうも革マル派っぽい人が近づいてくる。彼は「関國共」の前で立ち止まり、
「関國共さんは、何をやってるんですか?」
と一言。どのようにそこを言いつくろったかは知らないが、なんとか何事もなくやり過ごしたらしい。
春の暖かい日になると、ふと、このエピソードを思い出す。
#
ちなみに革マルというのはかなり大変なところだ。大学、そして大学に所属するサークル活動にかなりの力を持って影響を及ぼしていた。
夜の10時くらいだったか。友人と大変酔っ払って大学構内を歩いていたら、45度くらいに斜めに立てかけられた5m×7mくらいの巨大な革マル派の立て看板があった。
「○○大学当局の学費値上げを許さない!」といった内容だったと思うが、酔っ払った友人が突如その看板を駆け上った。すると、その看板の裏側から20人くらいの革マル員らしき人間がワラワラと飛び出してきて私たちはあっという間に首根っこを掴まれて校舎脇に連れて行かれ、尋問された。
数時間「単に酔っ払ってやっただけだから」と弁明するもひ弱そうな革マル員は我々ののど口をつかんで「ああ?」と問う。
最終的にはみんな散り散りにワーッと逃げ出したのだと思うが、なんともたいそうなエピソードだ。
革マルは今は大学の必死の追い出し策によって、拠点をつぶされ、魂を抜かれた感じとなっているが、相変わらず授業前に赤いビラを配ってるのかしらねえ。
#
今年大学に入った人はそろそろサークルが落ち着いたころでしょうか。
私のいた大学は多分日本でもサークルの活発さでは一二をを争うほどで、新入生の勧誘は、何百とあるサークルに加え、左翼団体の革マル派も加わり、それはもう大変な大騒ぎだった。
そうなると新入生歓迎の場所取りも必然的に熾烈な争いとなる。大学にきちんと場所を申請をしていても、その場所が勝手に取られたりするということも多い。
ある年、関口さんという人がその新勧の場所取りをまかされた。事前に大学に申請した場所にちゃんとガムテープ等で「サークルの場所はここですよ!」と印をつける役割だ。
関口さんは意気揚々と参加し、申請した場所を四角くガムテープで囲み、その中にガムテープでダイナミックに
「関口」
とそれはそれは大きな字を書いた。
翌日、サークル員が申請した場所に行くと大きな字で「関口」。みんな困惑するが、その中の一人が
「関口じゃあ、革マルに個人と思われてなめられます。」
と提案。ガムテープを取り出し、「関口」の上にビリビリとガムテープを貼っていく。そして、見る間に「関口」の字は
「関國共」
となった。意味はよく分からないが、とりあえず怖そうだ。これで今年の新勧は誰にも場所をよこどられることないだろう、とみんな胸をなでおろしていると、どうも革マル派っぽい人が近づいてくる。彼は「関國共」の前で立ち止まり、
「関國共さんは、何をやってるんですか?」
と一言。どのようにそこを言いつくろったかは知らないが、なんとか何事もなくやり過ごしたらしい。
春の暖かい日になると、ふと、このエピソードを思い出す。
#
ちなみに革マルというのはかなり大変なところだ。大学、そして大学に所属するサークル活動にかなりの力を持って影響を及ぼしていた。
夜の10時くらいだったか。友人と大変酔っ払って大学構内を歩いていたら、45度くらいに斜めに立てかけられた5m×7mくらいの巨大な革マル派の立て看板があった。
「○○大学当局の学費値上げを許さない!」といった内容だったと思うが、酔っ払った友人が突如その看板を駆け上った。すると、その看板の裏側から20人くらいの革マル員らしき人間がワラワラと飛び出してきて私たちはあっという間に首根っこを掴まれて校舎脇に連れて行かれ、尋問された。
数時間「単に酔っ払ってやっただけだから」と弁明するもひ弱そうな革マル員は我々ののど口をつかんで「ああ?」と問う。
最終的にはみんな散り散りにワーッと逃げ出したのだと思うが、なんともたいそうなエピソードだ。
革マルは今は大学の必死の追い出し策によって、拠点をつぶされ、魂を抜かれた感じとなっているが、相変わらず授業前に赤いビラを配ってるのかしらねえ。